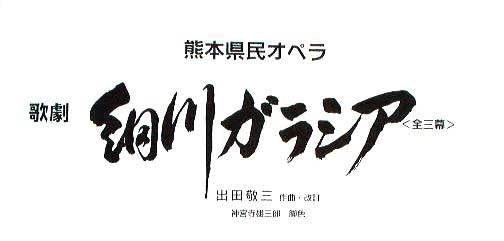
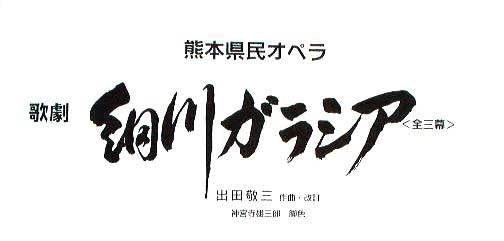
天正10年(1582年)6月2日、惟任日向守である明智光秀は時の権力者織田信長を奇襲し、自害に追い込む。世に名高い本能寺の変である。この事件は、時代に大きな波を立て、これを機に歴史の潮流は激しさを増していく。明智光秀は、勢いに乗じて一気に天下をねらうが、山崎の戦いで羽柴秀吉の軍勢の前に倒れる。破れて賊軍となった光秀は、謀反人の烙印を押されてしまう。光秀の娘である玉子(細川ガラシア)が、細川忠興のもとに嫁いでから4年目のことである。
| 歌劇「細川ガラシア」 出田敬三 作曲・改訂 |
||||
| 登場人物 | ||||
| 細川ガラシア | 明智光秀の娘、細川忠興の妻玉子 | セスペデス神父 | スペイン人、キリシタン宣教師 | |
| 清原マリア | 細川ガラシアの侍女頭 | ヴィンセンツォ三浦 | 日本人キリシタン宣教師 | |
| 小笠原少斉 | 細川家家老 | 巡礼の父 | 心の救いを求め巡礼する男 | |
| 正時 | 細川家家臣、清原に恋心をいだく | 巡礼の娘 | 救いを求め巡礼する男の娘 | |
| 高山右近内室 | キリシタン大名の夫人 | 飴売り | 町の人気者 | |
| 出雲のお加賀 | 出雲阿国の流れをくむ踊りの名手 | 武士 | 細川家家臣 | |
| 覚義 | 細川家家臣、迎えの使者 | 花見踊り | 町の人々 | |
| 花見の男 | 酔って巡礼にからむ男 | 細川多良 | 細川ガラシアの娘 | |
| 侍女 | 細川ガラシアの侍女 | 合唱 | 村人達、町娘達 他 | |
《第一幕:蓮の花咲くころ、細川領丹後の山深い味土野の隠れ里》
 忠興は、謀反人の娘となった玉子を、領内の山深い味土野の里に隠棲させていた(清原:呪わしき世なれや…)。いつ来るやもしれぬ追手の影におびえ暮らす味土野の隠れ城の毎日であったが、そこには清原と若侍正時の蓮の花のような淡い恋が芽生えていた。(清原・正時:戦いの庭にも…)。
忠興は、謀反人の娘となった玉子を、領内の山深い味土野の里に隠棲させていた(清原:呪わしき世なれや…)。いつ来るやもしれぬ追手の影におびえ暮らす味土野の隠れ城の毎日であったが、そこには清原と若侍正時の蓮の花のような淡い恋が芽生えていた。(清原・正時:戦いの庭にも…)。 しかし、都から遠く世間からも隔離された山懐とはいえ、今の玉子に安らぎの場はなかった(ガラシア・清原:生まれて二十年…)(侍女:今日まで数々のお苦しみに…)。すでに母や姉らは、「明智家を根絶やしに」という秀吉の命令により、亡き者とされていたのである。ある朝、味土野の隠れ城に見知らぬ者達が近づいているとの知らせがある。警護を任された家老小笠原少斉は、皆に守りを堅くするよう命ずる。が、それは秀吉の許しを受けた忠興からの迎えの使者であった。(覚義と使者の武士:この味土野の花を…)。玉子は、幽閉がとかれることを知らされ、2年ぶりとなる夫との再会に胸をときめかせるのであった(一幕フィナーレ/ガラシア・合唱・他全員:悩み多き年月の流れ…)。
しかし、都から遠く世間からも隔離された山懐とはいえ、今の玉子に安らぎの場はなかった(ガラシア・清原:生まれて二十年…)(侍女:今日まで数々のお苦しみに…)。すでに母や姉らは、「明智家を根絶やしに」という秀吉の命令により、亡き者とされていたのである。ある朝、味土野の隠れ城に見知らぬ者達が近づいているとの知らせがある。警護を任された家老小笠原少斉は、皆に守りを堅くするよう命ずる。が、それは秀吉の許しを受けた忠興からの迎えの使者であった。(覚義と使者の武士:この味土野の花を…)。玉子は、幽閉がとかれることを知らされ、2年ぶりとなる夫との再会に胸をときめかせるのであった(一幕フィナーレ/ガラシア・合唱・他全員:悩み多き年月の流れ…)。
《第二幕:桜の花咲くころ、大阪南蛮寺の門前》
玉子が夫と暮らすようになってから、幾度目かの春を迎えた。太閤秀吉の統治のもとに、 戦国の世は一応の終わりを見せる。南蛮寺門前の桜の下で、人々は口々に天下泰平をとなえ、花見に興じていた(合唱:桜さらさら…)。しかし、こ
戦国の世は一応の終わりを見せる。南蛮寺門前の桜の下で、人々は口々に天下泰平をとなえ、花見に興じていた(合唱:桜さらさら…)。しかし、こ の賑わいとは裏腹に、永年にわたる戦乱の時代がこのまま終わるとは、誰一人信じてはいなかった(高山右近内室・神父・三浦:また戦いになるでしょう…)。空虚な心に神父の教えを求めて南蛮寺へ集う者達、酒を花を楽しむ者達皆が、散りゆく桜の花に、明日終わるやもしれぬ浮き世の春を重ね見ていたのである(飴売り:ヤンレ ヤンレ…)(出雲のお加賀:日本舞踊/曲 フュージョン Ⅰ・Ⅱより(出田敬三作曲))。こんなとき、玉子は南蛮寺を訪れた(巡礼の父・娘:なむや なむや ふだらくや…)。かねてよりキリシタンの教えにひかれながらも、謀反人の娘であることに苦しみ、入信をあきらめかけていたが、神父に「すべての民の父はデウスである」と告げられる(ガラシア・清原・巡礼の父・娘:神父様はどこから…)。
の賑わいとは裏腹に、永年にわたる戦乱の時代がこのまま終わるとは、誰一人信じてはいなかった(高山右近内室・神父・三浦:また戦いになるでしょう…)。空虚な心に神父の教えを求めて南蛮寺へ集う者達、酒を花を楽しむ者達皆が、散りゆく桜の花に、明日終わるやもしれぬ浮き世の春を重ね見ていたのである(飴売り:ヤンレ ヤンレ…)(出雲のお加賀:日本舞踊/曲 フュージョン Ⅰ・Ⅱより(出田敬三作曲))。こんなとき、玉子は南蛮寺を訪れた(巡礼の父・娘:なむや なむや ふだらくや…)。かねてよりキリシタンの教えにひかれながらも、謀反人の娘であることに苦しみ、入信をあきらめかけていたが、神父に「すべての民の父はデウスである」と告げられる(ガラシア・清原・巡礼の父・娘:神父様はどこから…)。 玉子は、洗礼を決意した(ガラ
玉子は、洗礼を決意した(ガラ シア・清原:遠くの方から…)。(ガラシア:この世の秘密を…/たくらみと裏切りを…)。そして「人を愛して恵みを与える」「神が特別のおぼしめしを与える愛」とに意味を持つ「ガラシア」という洗礼名を授かり、新たな勇気が湧いてくるのであった。
シア・清原:遠くの方から…)。(ガラシア:この世の秘密を…/たくらみと裏切りを…)。そして「人を愛して恵みを与える」「神が特別のおぼしめしを与える愛」とに意味を持つ「ガラシア」という洗礼名を授かり、新たな勇気が湧いてくるのであった。
《第三幕:細川邸玉造の屋敷 夏の黄昏》
秀吉亡き後、再び戦乱の足音が高まり、時代は次なる天下人を求め始める(ガラシア:この世の暗い闇の中より…)徳川家康は全国統一をもくろみ、その先駆者としての上杉征伐のため関東に向かう。そのころ大阪玉造の細川邸ではガラシアと娘多良は平安で幸せなひとときを過ごしていた(ガラシア・清原・多良:奥方様これがイソップ物語でございます…) (侍女:みなしご達が…)(ガラシア・清原・侍女・多良:デウス様みめぐみを…)。
(侍女:みなしご達が…)(ガラシア・清原・侍女・多良:デウス様みめぐみを…)。 徳川に敵対する石田三成は、この時とばかりに兵を挙げ、これより天下分け目の決戦となる関ヶ原の戦いへと向かっていくのである。この国の運命が、ガラシアの運命が大きく変わることになる。関東遠征の徳川軍に加わり忠興不在となった細川邸は、石田軍挙兵の知らせにおびえた。やがて、石田の軍勢は、徳川軍に加担する大名の妻子らを人質に取ろうと、次々とその屋敷をお始める(少斉:万一の時には…)。キリシタンであるため自害を許されないガラシアは選択を迫られるが、意を決し、子供たちや侍女らを南蛮寺へと逃がすと、屋敷に火を放った。そして、最後の祈りを終え(ガラシア・合唱:サンタマリア今こそ…)、辞世を詠むと、家老少斉に介錯を命じ、従容として炎の中に身をおくのであった(ガラシア:散りぬべき…)。
徳川に敵対する石田三成は、この時とばかりに兵を挙げ、これより天下分け目の決戦となる関ヶ原の戦いへと向かっていくのである。この国の運命が、ガラシアの運命が大きく変わることになる。関東遠征の徳川軍に加わり忠興不在となった細川邸は、石田軍挙兵の知らせにおびえた。やがて、石田の軍勢は、徳川軍に加担する大名の妻子らを人質に取ろうと、次々とその屋敷をお始める(少斉:万一の時には…)。キリシタンであるため自害を許されないガラシアは選択を迫られるが、意を決し、子供たちや侍女らを南蛮寺へと逃がすと、屋敷に火を放った。そして、最後の祈りを終え(ガラシア・合唱:サンタマリア今こそ…)、辞世を詠むと、家老少斉に介錯を命じ、従容として炎の中に身をおくのであった(ガラシア:散りぬべき…)。
散りぬべきとき知りてこそ
世の中の
花も花なれ 人も人なれ
歌劇「細川ガラシア」について
このオペラは、原作ヘルマン・ホイヴェルス、原曲ヴィンセンツォ・チマッティで、この2人のよる版は、昭和15年東京・日比谷公会堂においてミュージックドラマとして公演。戦後、演出家神宮寺雄三郎氏の企画推進により4年がかりでオペラ化され、昭和35年・40年・41年・42年に上演されていたが、その後上演の機会はなく眠ったままになっていたが、この原曲の楽譜を作曲家の出田敬三氏(熊本音楽短期大学副学長・教授)が入手し、序曲、アリア、アンサンブル、終曲など新たに作曲、また原曲も大幅に編曲し直して音楽的にも現代的な作品に生まれ変わらせた。この出田敬三氏によって新しく生まれ変わった「細川ガラシア」は、昭和64年1月21・22日に熊本県民オペラとして、熊本県立劇場演劇ホールで初演され、同じ1月には東京・ゆうぽうとホールでも公演され、大きな反響を呼んだ。また、平成5年に熊本オペラ芸術協会設立10周年記念として再演。そして平成11年10月には熊本にて行われた第54回国民体育大会の公開競技スポーツ芸術主催事業として熊本県立劇場演劇ホールにて公演された。
歌劇「細川ガラシア」公演の記録
〔1989年1月21日・22日、27日〕初演
| 公演日 | 会場 | |||
| 1989年 | 1月21・22日 | 熊本県立劇場演劇ホール | ||
| 1月27日 | 東京・ゆうぽうとホール | |||
| 指揮・音楽監督 | 出田敬三 | |||
| キャスト | ||||
| 細川ガラシア | 常森寿子、小林なほみ | |||
| 細川多良 | 池田真弓、田代淑子 | |||
| 清原マリア | 古里聖子、高橋侑子 | |||
| 小笠原少斉 | 平和孝嗣、平江純一 | |||
| 正 時 | 五十嵐 修、宮田武久 | |||
| 覚 義 | 久保山尉介 | |||
| セスペデス神父 | 川畑 博 | |||
| あめ売り | 尾上知久 | |||
| ヴィンセンツォ三浦 | 藤本周一 | |||
| 巡礼の父 | 山本雄二 | |||
| 巡礼の娘 | 竹田富美子、高木真由美 | |||
| 花見の男 | 渡辺恭士、松村直寛 | |||
| 侍女 | 藤岡久美子、工藤和美、村上真理、高木千鶴子、平田恵美 崎元啓子、井島美貴、林 知江美 |
|||
| 家来・花見の群衆 | 田代祐基、馬原敬二、渕上秀樹 桑本昭憲、御崎文男、椎葉直樹 |
|||
| 花見おどり | 藤豊会 | |||
| 合唱 | 西 久美子、藤田悦子、藤井ルミ、上田乃子、北野紀久子 鈴木元子、中谷賀代子、岩山美江、野副史枝、原田千春 |
|||
| 熊本音楽短期大学カンマーコール 熊本オペラ芸術協会合唱団 |
||||
| エキストラ | 中嶋隆光、浜田 悟、倉本圭志 | |||
| 特別出演(高山右近御内室) | 細川佳代子 | |||
| 箏 | 古川郁代、田島涼子 | |||
| 管弦楽 | 熊本音楽短期大学管弦楽団 | |||
| 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 | ||||
| スタッフ | ||||
| 総監督 | 出田憲二 | |||
| 演出 | 亀井隆一郎 | |||
| 美術 | 吉本政弘 | |||
| 振付 | 藤間勘太女 | |||
| 謡曲指導 | 桜間金太郎(金春流) | |||
| 大道具制作 | (有)吉本美術 | |||
| 技術 | 松崎照明研究所in九州 | |||
| 衣装 | 東京衣装株式会社 | |||
| 小道具 | 株式会社藤波アートセンター | |||
| かつら | 株式会社山田かつら | |||
| スクリプト | 尾上知久 | |||
| 舞台監督 | 大畑千秋 | |||
| 練習ピアニスト | 大石陽子、友永和恵、中村直子、別城博士、吉川由香 | |||
| 仕舞指導 | 築地豊治 | |||
| 作法指南 | 小堀富夫(茶道肥後古流) | |||
| 演技指導 | 渡辺恭士、久保山尉介 | |||
〔1993年9月4・5日〕熊本オペラ芸術協会設立10周年記念公演
| 公演日 | 会場 | |||
| 1993年 | 9月4・5日 | 熊本県立劇場演劇ホール |
||
| 指揮・音楽監督 | 出田敬三 | |||
| キャスト | ||||
| 細川ガラシア | 工藤和美、西森由美 | |||
| 清原マリア | 平田恵美、古里聖子 | |||
| 小笠原少斉 | 平和孝嗣 | |||
| 正 時 | 伊達英二 | |||
| 覚義 | 久保山尉介 | |||
| 日比屋モニカの母 | 高橋嘉子 | |||
| セスペデス神父 | 川畑 博、平江純一 | |||
| 特別出演(高山右近御内室) | 細川佳代子、細川裕子 | |||
| あめ売り | 尾上知久 | |||
| ヴィンセンツォ三浦 | 渕上秀樹、川畑 博 | |||
| 侍女 | 湯野由美子、森崎ひとみ、篠原恵理 小山祐喜子、井島美貴 |
|||
| 巡礼の父 | 松森 光 | |||
| 巡礼の娘 | 高木麻由美、岩本祐子 | |||
| 花見の男 | 渡辺恭士 | |||
| 武士 | 渕上秀樹、竹下浩二、桑本昭憲 中嶋隆光、御崎文男、南 治郎 |
|||
| 笛の伝介 | 蔦谷栄一 | |||
| 花見おどり | 藤豊会社中 | |||
| 細川多良 | 松永涼子、春野祐子 | |||
| 子供達 | 御船みどりの森少年少女合唱団 | |||
| 特別出演(高山右近内室) | 福島恭子 | |||
| 特別出演(出雲のお加賀) | 藤間豊大郎 | |||
| 合唱 | 熊本音楽短期大学女声合唱団カンマーコール 熊本音楽短期大学男声合唱団 熊本オペラ芸術協会合唱団 |
|||
| 管弦楽 | 熊本交響楽団 | |||
| スタッフ | ||||
| 総監督 | 出田憲二 | |||
| 演出 | 亀井隆一郎 | |||
| 演技指導 | 渡辺恭士、久保山尉介 | |||
| 舞踊振付 | 藤間富士齋 | |||
| 謡曲・仕舞指導 | 築地豊治 | |||
| 作法指南 | 小堀富夫 | |||
| 子役音楽指導 | 上村澄春(熊本児童合唱団) 荒川 弘(熊本少年少女合唱団) |
|||
| 美術 | 野田英二 | |||
| 照明 | 浦部英正 | |||
| 大道具制作 | (有)吉本美術 吉本政弘 | |||
| 照明技術 | 松崎照明研究所in九州 | |||
| 衣装 | 東京衣装株式会社 | |||
| 小道具 | 株式会社 藤波アートセンター | |||
| かつら | 株式会社 山田かつら | |||
| 演出助手 | 尾上知久 | |||
| 舞台監督 | 野口ひろとし | |||
| 練習ピアニスト | 平田康一、川口みさき、大石陽子 別城博士、吉川由香 |
|||
| ライブラリー | 山田隆彦 | |||
| インスペクター | 小林高彦、武井 脩 | |||
〔1999年1月21日・22日〕細川ガラシア没後400年、第54回国民体育大会公開競技スポーツ芸術主催事業
| 公演日 | 会場 |
| 1999年1月21・22日 | 熊本県立劇場演劇ホール |
| 指揮・音楽監督 | 出田敬三 |
| キャスト | |
| 細川ガラシア | 工藤和美、水野貴子 |
| 清原マリア | 村川和美、原田千春 |
| 小笠原少斉 | 勝部 太 |
| 正 時 | 宮田武久 |
| 特別出演(高山右近御内室) | 細川佳代子、細川裕子 |
| 特別出演(出雲のお加賀) | 藤間豊大郎 |
| 覚 義 | 築地豊治 |
| 花見の男 | 堀田 清 |
| 侍女 | 朽木洋子、赤星百合子、佐伯文子、高松知江美、前田宏子 福嶋由記、緒方丈子、小山祐喜子、福川香織、桑原理恵 |
| セスペデス神父 | 川畑 博 |
| ヴィンセンツォ三浦 | 藤本周一 |
| 巡礼の父 | 松岡 聡 |
| 巡礼の娘 | 池田真弓、木下 愛 |
| あめ売り | 村田憲昭、照谷 陽 |
| 武士 | 田尻淳一郎、田浦康宏、緒方宏明、坂本和隆 |
| 花見おどり | 藤豊会 |
| 細川多良 | 山本夏妃(熊本児童合唱団) 西宮結希(熊本少年少女合唱団) |
| 合唱 | 熊本音楽短期大学女声合唱団カンマーコール 熊本音楽短期大学男声合唱団 |
| 管弦楽 | 熊本音楽短期大学管弦楽団 K.I.Q.電子オルガンカルテット (日野徳子、西尾真紀、西島 愛、川島美由紀) |
| スタッフ | |
| 総監督 | 出田憲二 |
| 演出 | 渡辺恭士 |
| 作法指南 | 小堀富夫 |
| 舞踊振付 | 藤間富士齋 |
| 謡曲・仕舞指導 | 築地豊治 |
| コーディネーター | 大江捷也 |
| 演出補佐・舞台監督 | 尾上知久 |
| 美術 | 野田英二 |
| 照明 | 英正 |
| 大道具制作 | M.V.P |
| 照明技術 | 松崎照明研究所in九州 |
| 音響 | 上野 敬、吉田真介 |
| 衣装・小道具・かつら | 田口良二・日本芸能美術株式会社 |
| バックステージ・チーフ | 五島和幸 |
| バックステージスタッフ | 松村俊雄、牧本祐輔、近藤治道 |
| マネージャー | 酒井勝興、武井 脩、甲斐田鶴子 |
| アドヴァイザー | 高橋嘉子、蔵原スミ子、小林高彦 |
| 稽古ピアニスト | 別城博士、原村千秋、吉良千波、中山京子 |
| 練習指揮 | 荒木由美(舞台袖合唱指揮)、山田隆彦 |
| ライブラリー | 柏尾剛徳 |
| オーケストラインスペクター | 上田愛彦 |
| インスペクター | 平田エミ |
※このデータは公演当時のプログラムをもとに作成していますので、現在と若干表記が異なる部分がありますことをご容赦下さい。